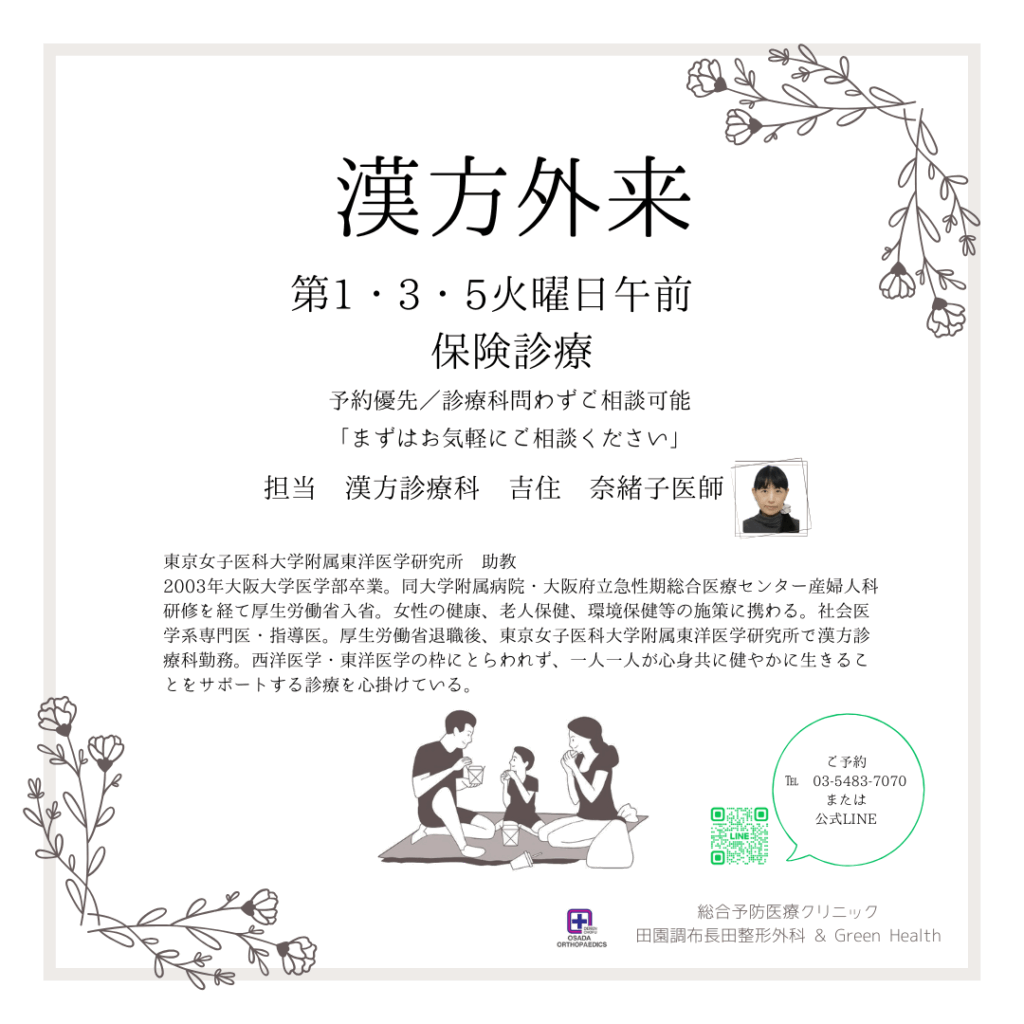年齢を重ねるにつれて、「夜中に何度も目が覚める」「朝早くに目が覚めて眠れない」といったお悩みをよく伺います。これは加齢に伴う自然な変化のひとつとも言えますが、生活の質に影響することもあるため、睡眠の質を良くすることは重要です。今回は、東洋医学を中心に原因と対策についてご紹介します。
【東洋医学からみた原因】
東洋医学では、陰陽の気の交代が睡眠と覚醒のリズムを支配すると考えられています。陽気が過剰で夜になっても収まらない場合や、夜に盛んになるべき陰気が不足している場合に安眠ができなくなります。高齢の方に多い中途覚醒や早朝覚醒には、次のような背景があることが多いです。
1. 腎の力が弱まる(腎陰虚):年齢とともに体を潤し落ち着かせる「陰」が不足し、眠りが浅くなります。
2. 心と腎のバランスの乱れ(心腎不交):体を静める力が弱まり、夜中に目が覚めやすくなります。
3. 心と脾の弱り(心脾両虚):長年の疲労や考えすぎなどで「気血」が不足し、眠りを保てなくなります。
【代表的な漢方薬】
症状や体質に応じて、保険診療で処方できる漢方薬があります。
■ 入眠障害(寝つきが悪い)
– 抑肝散:神経が高ぶりイライラして寝つけないタイプに。
– 柴胡加竜骨牡蛎湯:不安や緊張が強く、なかなか眠れないタイプに。
■ 中途覚醒・早朝覚醒
– 酸棗仁湯:夜中に目が覚めやすい、眠りが浅いタイプに。
– 桂枝加竜骨牡蛎湯:神経が高ぶり夢が多い、途中で目が覚めやすいタイプに。
– 帰脾湯:疲れやすく夢が多い、気血不足タイプに。
【実は「眠れている」場合も】
本人は「眠れなかった」と感じていても、実際には必要な睡眠がとれていることがあります。特に高齢になると浅い眠りが増えるため、夜中に目が覚めた記憶が強く残り、「ぐっすり眠れていない」と感じやすいのです。しかし、このタイプの方は日中の活動に支障がなく、元気に過ごせていることが多いです。
【養生の工夫】
– 朝日を浴びる:体内時計を整えることで夜の眠りを深めます
– 日中の軽い運動:気血の巡りを良くして熟睡を助けます
– 昼寝は20〜30分以内に:長すぎる昼寝は夜の睡眠を妨げてしまいます
– 寝る前はリラックス:スマホやテレビを控え、深呼吸や読書、音楽を聴くなどのリラックス習慣で心を落ち着けます
– 夕食は軽めに:遅い時間に消化の悪い食事は避けましょう
【西洋医学からみた補足】
– 加齢により深い眠り(ノンレム睡眠)が減るため、夜間の覚醒が増えるのは自然なことではあります。
– 不眠の背景に頻尿、痛み、睡眠時無呼吸症候群などが隠れている場合もあり、必要に応じて検査や治療が検討されます。
【まとめ】
不眠は、入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒に分けられます。高齢の方の不眠は、東洋医学では「腎、心、脾の弱り」「気血の不足」などが背景にあると考えられ、西洋医学では「加齢に伴う自然な睡眠の浅さ」が中心ですが、睡眠時無呼吸症候群など他の疾患が隠れている場合もあり、注意が必要です。一方で、日常生活に支障がない場合は「眠れていない感覚」が強いだけで、実際には必要な睡眠がとれていることもあります。
養生の工夫と体質に合った漢方薬で、安心して日々を過ごせるようにサポートしていきますので、不眠が気になる方は一度ご相談ください。